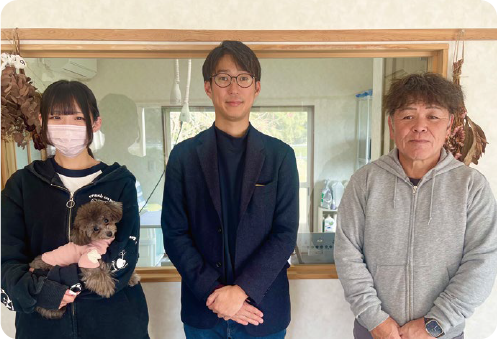シェルターに保護される犬の多くは、健康であるとは限りません。病気の治療が必要だったりします。さらに、新しい家族を見つけるためには、ワクチン接種や避妊去勢は必要不可欠です。でも、こうした医療ケアを続けるには、それなりの費用がかかります。アメリカでは、寄付や助成金を活用しながら、シェルターが医療費をしっかり確保できる仕組みが整っています。一方、日本では、行政の補助がある団体もありますが、民間の保護団体は個人の寄付に頼る部分が多いため、資金不足が課題になっています。どうしてこんな違いがあるのか?そして、日本のシェルターでも安定して医療費を確保するにはどうしたらいいのか?
アメリカの例を参考にしながら、考えてみましょう。

アメリカでは、シェルターの運営資金の多くが寄付や助成金、低価格診療サービスなどによって支えられています。特に、寄付文化が根付いているため、多くの人が個人で支援を行い、企業も動物福祉を支援するプログラムを積極的に実施しています。
主な資金源内訳
個人寄付
アメリカでは、シェルターへの寄付が
日常的に行われており、多くの人が気軽に
寄付できる体制が整っています。
-
「1ドルから寄付できる」仕組みが普及
スーパーやペットショップで会計の際に
「寄付しますか?」と毎回聞かれる。 - 遺産寄付(亡くなった後に資産の一部を寄付)
-
企業のマッチング寄付
(従業員が寄付した額を企業が上乗せする)
企業スポンサー・助成金
企業がシェルターを支援するケースが多い。
- ペットフードメーカーがフードを寄付
- 大手企業が助成金を提供
- 地元企業がイベントやグッズ販売を通じて資金提供
低価格診療サービスの提供
-
多くのシェルターでは、一般の飼い主向けに
低価格のワクチン接種や避妊・去勢手術を提供し、
その収益を保護犬の医療費に充てています。
イベントやグッズ販売
地域の人が参加しやすいイベントを開催し、
入場料など寄付にしたりグッズ販売で
寄付をつのる。
-
チャリティーイベント
(譲渡会、マラソン、寄付型コンサートなど) -
シェルターオリジナルグッズの販売
(Tシャツ、トートバッグなど)
アメリカのシェルター[ASPCA]
2023年資金源

出典: ASPCA

大口寄付者の
名前を掲示し、
シェルター支援への
貢献を称えるボード

日本の動物シェルターはアメリカに比べて、資金調達の仕組みが限られているため、医療費や運営費の確保が難しいのが現状です。特に3つの課題が大きく影響しています。
-
1
行政からの
助成金が少ない日本では自治体からの助成金があるものの、支給額は少なく、対象となる施設も限られています。
anifareは助成金は一切受け取っておらず、完全にみなさんの寄付で運営させていただいております。 -
2
個人寄付が少なく
寄付文化も
根付いていない日本では日常的に寄付する習慣や、文化が根付いていません。寄付=大きな額というイメージがあり、少額から気軽に支援する文化がほとんどないです。
-
3
企業支援や
スポンサーが少ないアメリカでは多くの企業がCSR活動の一環としてシェルターを支援していますが、日本ではまだ協力企業が非常に少なく、ペット関連企業や地域の企業と連携する仕組みが十分に整っていません。

anifareはより持続可能なシェルターを目指しています。私達は行政の助成金を一切受け取らず、完全に 寄付と自主的な資金調達だけで運営しています。しかし、保護犬に十分な資金を確保できておらず、医療費や施設維持、人員確保のための安定したご支援が必要な状況です。これからは寄付だけに頼らず、企業との連携や自主収益の強化にも力を入れ、より多くの保護犬に医療や安心できる環境を提供 できるよう取り組んでいくことを目指していきます。

anifareシェルター資金源
施設の維持・新シェルター増設
犬が快適に過ごせる清潔な環境を整え、
ストレスの少ない生活を提供。
収容可能な頭数を増やし、より多くの保護犬を
受け入れられる体制を強化できる。
医療費のカバー範囲が拡大
緊急手術や治療が必要な犬をサポートし、
シェルターでワクチン接種や
フィラリア予防の医療も提供できる。
1頭あたり20万円の医療費かがかるとすると、
寄付額が増えると、より多くの保護犬の医療費をカバーできる。
1,000万円の寄付で約50頭、5,000万円なら250頭の医療を支援可能。


日本の動物シェルターは、資金不足が最大の問題点ですね。
行政の助成金が少なく、寄付文化も十分に根付いていないため、保護犬が快適に暮らせる施設の維持や
保護犬の医療費の確保が難しい状況です。アメリカでは、企業スポンサーや小額寄付の仕組みが整い、
安定した運営が可能ですが、日本では支援の仕組みを広げ、理解を深めることが今後の課題だと思います。
1人ひとりの意識を変え、寄付や支援の輪を広げることが、より多くの保護犬を救う第一歩。
未来のために、今できることから始めてきたいです。